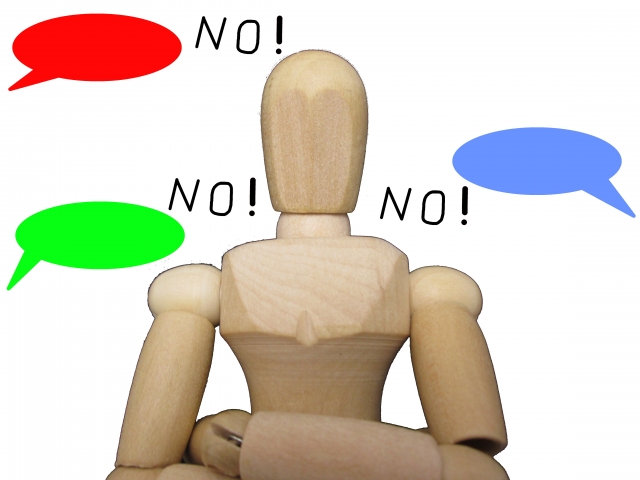【人材】時間の考え方とスタッフについて
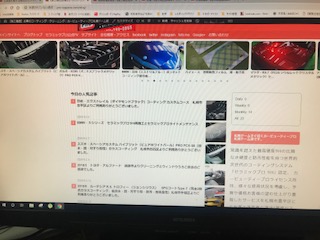
ページコンテンツ
時間について
最近ではお客様より「ブログ、頑張ってますね」といった嬉しいお声をいただくことが増え、心より感謝申し上げます。
シートクリーニングや緊急対応、ヘッドライトクリーニングなど、比較的短時間で完了する作業については、日々の業務の中でなかなかブログでご紹介できておりません。
一方で、1日以上お預かりする案件に関しては、お客様へのご報告も兼ねて、なるべく記録を残すよう心がけております。ただし、1〜2月は確定申告の準備等により更新が遅れてしまうこともあり、その点はご容赦ください。
ブログ更新は、お客様への情報提供だけでなく、自分自身が初心を忘れずにいるための大切な記録でもあります。このような「書き残す習慣」は、毎日のスケジュールに組み込むようにしており、時間の使い方そのものが業務全体に反映されていると感じています。
もちろん、予期せぬ出来事やイレギュラーな対応も多く、計画通りに進まない日もあります。しかしながら、時間の「軸」をしっかり持っていれば、意外と数分単位でのリカバリーも可能であるという実感があります。
ブログについて
ブログは施工記録として公開しておりますが、決して自己満足のためのものではなく、お客様へのご報告としての意味合いを持たせております。
当店、カービューティープロ札幌ドーム前では、作業中の見学をご遠慮いただいております。そのため、施工の流れやお客様が気になるポイントをできる限り丁寧にお伝えすることで、「見えない部分の可視化」と「安心感の提供」を目指しております。
お客様にとって分かりやすく、親しみやすい、いわゆる“ユーザーフレンドリー”な情報発信を心がけております。
作業時間の考え方
カーディティール業では様々な個性を持った方が多いですが、中には「こだわり」と「意固地」を勘違いされている方が非常に多いです。
「こだわり」とは、単なる自己満足ではなく、“良い仕事をするための方向性”を指すものだと考えています。
良い仕事とは一見シンプルに思えるかもしれませんが、実際には非常に奥が深く、最終的には「お客様の満足度」によって評価されるものだと思います。
たとえば、ある部材を美しく仕上げようとして、理論もなくひたすら時間をかけた結果、10時間かかったとしましょう。お客様がその仕上がりに満足してくだされば、それはそれで良いかもしれません。
しかし、その作業に対して時給8,000円の工賃が発生するとしたら、果たしてそのコストはお客様にとって妥当なものでしょうか?
一方で、しっかりと技術と理論を習得し、同じ作業をわずか15分で仕上げることができれば、料金は2,000円程度で済み、同じ満足をより効率的に提供することが可能になります。
これは、外装研磨にも通じる考え方です。当店のようにカービューティープロ、セラミックプロの正規ライセンスを持つ施工者は、徹底した理論と技術を叩き込まれており、それが“最短で最良”の結果を導く支えとなっています。
開業直後から高品質な施工が可能であるのは、そうした理論に裏付けされた基本がしっかりと身についているからこそなのです。
理論がなければ、どれだけ時間をかけても結果は安定せず、10時間かけても満足いただけない仕上がりになってしまう可能性すらあるのです。
人材について
以前、某コーティング店から当店へ面接に来られた方の例があります。
その方は「研磨作業は最低でも8時間かけるのが当たり前で、それが最高の仕上がりに繋がる」と考えており、自らの“こだわり”として語っていました。
しかし、詳しくヒアリングを行ったところ、実情は異なっていました。
実はその研磨作業、内容を掘り下げていくと、油分の多いコンパウンドで洗車キズを一時的に埋めているだけ。
つまり、弱い機材を使って長時間をかけ、表面に油分を塗り込んでツヤを出しているに過ぎない手法だったのです。
確かに、それも一つのアプローチではあり、状況によっては“ケースバイケース”で通用することもあるでしょう。
しかし、それをもって「技術」と呼ぶには無理があります。
こういった“技術と呼べない方法”が、正しい施工だと誤解されているケースは実に多いと感じます。
時間をかけていれば良い、という思い込みが、本質を見失わせてしまっているのです。
研磨は様々な考え方がありますが、埋めるコンパウンドと埋めるコーティングをされる場合もありますので注意しましょう。もちろんお客様が希望されればですが、技術力とは違い考え方ですので‥
当店では、その作業方法を“時間の無駄”と判断し、不採用とさせていただきました。
ご本人は「こだわり」と表現していましたが、カービューティープロ札幌ドーム前の基準から見れば、技術レベルは低いと評価せざるを得ません。
同じ仕事量であれば、私たちは1時間で終わらせるだけの理論と技術を備えております。
意味のない“こだわり”や、理論に基づかない自己流の作業は、結果的に「百害あって一利なし」。
それではお客様に真の満足を提供することはできません。
コーティング業界の闇の部分

「時間をかけて丁寧にやります」という言葉。
一見すると誠実な姿勢に聞こえますが、実はその裏に**“理論が無いから時間がかかっている”という現実が隠れている場合も少なくありません**。
つまり、技術や理論が未確立なまま作業時間を引き延ばし、それを“丁寧さ”とすり替えてしまっている――そんなケースもあるのです。
中には、意図的に時間工賃を増やすために長時間施工を装うような業者も存在します。
実は店長自身がまだ一般ユーザーだった頃、ある店舗にコーティングを依頼した際に、「時間をかけて丁寧に作業します」と説明を受けました。
ところが、たまたまその店の前を通りかかった際、スタッフが店舗前でキャッチボールをしているのを複数回目撃…。
施工期間は1週間以上とのことでしたが、その実態に強い疑問を感じました。
業界に入り、あの時の違和感の正体がはっきりと理解できました。
また、個人経営の店舗では、お客様との長話が作業時間に影響していたり、私用の通院時間や私生活との境界が曖昧になっていたりするケースも見られます。
そうした“公私混同”が工賃に含まれているとしたら、お客様にとっては本末転倒です。
一人親方など一人で作業を行っている場合
管理体制がしっかりしていない職場では、「時間無制限で納得いくまで仕上げます」といった言葉がよく使われがちです。
一見、丁寧な姿勢に聞こえるかもしれませんが、実際には時間に対してルーズな体質が背景にあることが多く、結果として施工品質や信頼性の低下につながっているケースをよく目にします。
実際、そうしたお店に突然訪問してみると、店舗が不在だったり、家庭の用事や私用、果ては通院まで作業時間に含まれているような状況も見受けられます。
しかし、カーディテイリングの作業というのは、経験と実績、そして日々の工夫によって“作業時間は短く、仕上がりはより高品質に”なるのが本来の姿です。
作業効率が上がるからこそ、プロテクションフィルムなどのオプションメニューを導入できたり、お客様の多様なニーズに応えることが可能になります。
逆に、1年、2年、数年と経過しても何も変わらない、進歩が見られないというのは、裏を返せば「成長していない」ということ。
これは、人を育てる立場にあるからこそ、日々強く実感していることでもあります。
詳しくはこちらもご覧ください。
自称こだわり?
ここで一つ、重要なキーワードがあります。
それは「自称こだわり」です。
本来、“こだわり”とは自分で語るものではなく、お客様や第三者が、その仕事ぶりを見て自然と感じ、評価してくれるものです。
にもかかわらず、自分自身で「自分はこだわってます」と語る人の多くは、実際には“こだわり”というよりも意固地になってしまっているケースが少なくありません。
このような“意固地なこだわり”は、本人の中では「頑張っている」「丁寧にやっている」と思い込んでいる場合が多いのですが、実際には成長が止まっていることも多く見受けられます。
また、そのような方に共通する傾向として、他人に対して押しつけがましい発言が目立つようになるのも特徴です。
「これが正しい」「こうやるべき」といった一方通行の考え方では、柔軟性も学びも生まれません。
真のこだわりとは、相手(お客様)に伝わって初めて評価されるもの。
自称ではなく、結果で語れるプロでありたいと、私たちは考えています。
こだわりと意固地は別物です。
カービューティープロ札幌ドーム前の採用基準
車好き洗車好きだけではNG!
当店では、「車が好き」という気持ちだけでは務まりません。
もちろん、車好きであることは悪いことではありませんし、大切な要素のひとつです。
しかし、私たちが手がけているコーティングや研磨は、単なる“見た目の美しさ”を追求するものではありません。
コーティングはお車を守るためのものであり、研磨はダメージを受けた塗装面をリフレッシュし、本来の美しさと保護機能を取り戻すための技術です。
これらの作業には、一時的な満足だけでなく、長期的な視点と責任感が求められます。
だからこそ、ただ“車が好き”というだけでなく、お客様のお車をどれだけ大切に思えるか、その先の価値を見据えて施工できるかが、当店では何よりも重要なのです。
また、車好きな方ほど、さまざまな“うんちく”に詳しい傾向があります。
それ自体を否定するつもりはありませんが、実際に長年乗ってこられたオーナー様に対して、表面的な知識を語ってしまえば、不快な思いをさせてしまう可能性もあります。
大切なのは、知識の多さではなく、その車をどれだけ大切に扱ってきたか、そして車に対してどれだけ敬意を持てるかです。
個人の嗜好や知識量ではなく、お車に向き合う姿勢や実体験の重みこそが、私たちの仕事において求められる資質だと考えています。
【経験者の場合の採用基準】
当店では、経験者の方に対しては、シングルアクションポリッシャーのみを用いて、トヨタ202ブラックの下地処理を80%以上の仕上がりレベルで行えることを求めています。
また、未経験者のご応募も歓迎しております。
これは、中途半端な技術レベルの経験者を採用すると、店舗全体の施工品質やレベルが低下してしまうリスクがあるためです。
当店では、施工レベルの維持・向上を最優先に考えており、適切なスキルを持つ方、あるいはこれからしっかりと学ぶ意欲のある方を求めています。
【次のいずれかに該当する方は、ご応募をお断りさせていただいております】
経験者の場合
- 「美装」という名称で、ディーラーや中古車販売店のコーティング出張業務に携わっていた方、またはその現場で従事されていた方。
こうした環境では、コストや時間の制約から低レベルな技術や価値観が身につきやすく、当店の基準に合ったレベルへの矯正が難しいと判断しております。 - フランチャイズ施工店での勤務経験者。
特に北海道の環境においては、東京や関東の本部所在地で採用されている施工技術・理論が十分に役立たない場合が多く、癖がついてしまった技術の矯正が困難です。 - DIY洗車愛好家の方。
自分なりのこだわりを持ち、お仕事にされたいお気持ちは理解しますが、技術は常に進化しており、数十年前の施工法を最新と信じている方も少なくありません。
また、身についた癖の強い技術は、当店の基準に沿った施工技術への適応が難しい場合があります。 - 単なる「車好き」の方。
当店では車好きだけでは十分ではありません。
お車を大切に扱う意識と責任感が何よりも求められます。
【コラム】接客及び人材について
私自身が自動車免許取り立ての頃、自動車関連業者様へ相談すると職人気質の方が多く、その対応はあまり良い物は言えませんでした。しかし技術力は良い傾向にあったので自信の表れと解釈しておりました‥
詳しく下記リンクより
コーティングのお仕事を考えられている方にアドバイス
「仕事に貴賎なし」と言われますが、確かに社会全体の視点で見ればその通りでしょう。
しかし、コーティング業界においては、その言葉では語れない“技術と環境の差”が確実に存在し、それが将来を大きく左右する要因になり得ます。
「コーティングの仕事をやってみたい」と考えるきっかけや動機は、人それぞれだと思います。
ですが、どこで・誰のもとで学び、どのような環境で働くかによって、その後の人生が180度変わってしまう――それほど重要な分岐点になるのが、この業界の現実です。
たとえば、「セラミックプロ9H」という世界的に認知された高品質コーティング剤。
札幌市内では、この名前を使った“偽物”の施工が確認されているという実態があります。
正規ライセンスのない業者が、正規品ではない液剤を用いて「セラミックプロ9H」を名乗る――これはお客様を欺くだけでなく、業界全体の信用を損ねる重大な問題です。
正しい知識、正規の技術、誠実な姿勢。
これらが備わっていない環境で働いてしまえば、自分の将来も、お客様の信頼も、築き上げることはできません。
セラミックプロ9Hは、世界的に認知された高性能ガラスコーティングであり、施工には厳正な審査と技術レベルの確認が求められます。
つまり、正規施工店として認定されるには、一定以上の技術力・知識・責任感が必要であり、それがクリアできなければ、そもそも加盟自体が許されません。
しかし一部では、認定されなかった業者が、微妙な名称や説明のニュアンスを変えて“なんちゃってセラミック”を名乗ったり、インターネットで購入した安価なコーティング剤にオリジナルの名前をつけて販売するといった行為が見られます。
こうした安易で不誠実な方法を容認する現場で働くことが、将来にどのような影響を与えるのか――想像してみてください。
人は、日々の環境と周囲の行動に大きく影響を受けます。
つまり、技術力がなく、正当な評価を得られない現場で過ごし続ければ、自身の成長が止まり、「誰からも認められない人」になってしまうリスクすらあるということです。
私たちの業界は、「見て覚える」「真似て育つ」世界でもあります。
だからこそ、どんな現場で、どんな人から学ぶかが、あなたの将来を大きく左右するのです。
安易な選択は、時に**“取り返しのつかない遠回り”**になることもあります。
どうか、慎重に、そして真剣に、自分の進む道を選んでください。
コーティング屋さんの現在所有されているお車は?
コーティングをご依頼される際には、ぜひその店舗の店主・店長・従業員が実際に乗っているお車を見せてもらってみてください。
たとえば旧車を丁寧に維持されている方であれば、水分や錆への配慮はもちろん、保管環境やセキュリティーに対する意識もしっかりされているはずです。
こうした方は、“実際に車と向き合っている経験”に裏打ちされた施工”ができる可能性が高いと考えられます。
一方で、新車を頻繁に乗り換えているだけの方の場合、車がどのように傷み、どのように劣化するのかといった実体験に基づく理解が乏しいことが多いのが現実です。
また、たとえ車好きであっても、実際に所有し、維持管理を続けて初めてわかる「不満点」や「改善点」が見えていなければ、それは“薄い知識だけを持った施工者”で終わってしまいます。
こうした場合、目の前の施工だけに意識が偏りがちで、広い視野や長期的な視点を持てない“浅い施工者”が生まれやすくなるのです。
中には、自分では車を買わずに知識や文句だけを口にするような方も存在します。
そのような姿勢では、お客様のお車に対して“本当の意味での思いやり”を持って向き合うことはできません。
施工者の「人となり」や「日常の姿勢」こそ、施工技術以上に信頼すべき判断材料になることもあるのです。

平成3年式のYJラングラーとハーレーを所有しています。
ラングラーに関しては、自ら購入してからすでに30年以上が経過しました。
このモデルは、かつて長渕剛さん主演の映画『オルゴール』で砂浜を走るシーンに登場したものと同型式で、当時はなんとホンダのディーラーで販売されていたという背景があります。
こうした旧車を長年にわたって維持してきた経験は、**単なる車好きでは得られない「経年劣化の知識」や「実用上の工夫」**を与えてくれました。
その経験こそが、お客様のお車と真摯に向き合うための大切な礎となっています。

札幌へ戻ってからは、以前から好きだったダイハツ・コペンを購入し、休日にはオープン走行を楽しんでおりました。
旧車の部類に入るモデルではありますが、とても愛着があり、特別な1台でした。
しかし、実生活の中では理想だけではいかない部分もあり、2022年の大雪の際、FF車での雪国生活に限界を感じ、現在はRAV4アドベンチャーに乗り換えております。
RAV4は使い勝手に優れる一方で、外装に多用されている樹脂パーツに対するコーティングの「メリット・デメリット」も、自身の車を通じてしっかり体感しています。
こうした日常的な実体験こそが、お客様へのご提案や施工内容にリアルな説得力をもたらしてくれていると感じています。

サーキット走行で徹底的に使い込んだスカイラインGT-R(R34)を、現在でも大切に所有しています。
単なるコレクションではなく、過酷な環境での車両挙動や塗装面の変化、パーツへのダメージなど、リアルな使用状況を経験した上でのメンテナンス知識と技術を培ってきました。
さらに現在は、プロテクションフィルムや各種コーティングの実験・開発用途としてGRヤリスを導入し、
実際の車両を用いた試験・施工比較など、お客様へ提供するサービスの質向上に活用しております。
「現場で得た知見」と「実車を通じた継続的な検証」を重ねることで、机上では得られない確かなノウハウを蓄積しております。
経歴は嘘をつきません。
とくに私たちのような職人業においては、それが何よりの信頼の証です。
コーティングとは、単に見た目を整えるものではなく、お車そのものを守るための施工です。
また、研磨は傷んだ塗装面をリフレッシュし、本来の美しさと保護性能を取り戻すために行われます。
いずれも“今だけきれい”を目指すのではなく、長期的な視点で大切に考えるべき技術です。
しかし、長期的視点を持たず、手が届かない・洗えないような部分にまで自己満足のためだけにコーティングを施工し、数年後に黄ばみや劣化が出てきた際に「洗車の仕方が悪い」などと開き直るケースがあるのも、残念ながら業界の現実です。
また、免許を取りたての10代ではあるまいし、多くの方は日々の生活の中で“洗車にたっぷり時間をかける”余裕がないのが実情です。
それにも関わらず、そうした現実を無視した理想論を語るだけの説明も多く、私たちはそういった姿勢には強い疑問を持っています。
現実を踏まえ、持続可能な施工とアドバイスができてこそ、本当に信頼される職人だと考えています。
2025年現在、長期的視点でのカーケアを考えるうえで「プロテクションフィルムを施工できる技術があるか否か」は、非常に大きな分岐点になっています。
たとえば、ヘッドライトの黄ばみを研磨するケースがあります。
確かに一時的には美しくなりますが、表面のハードコートがすでに劣化している場合、数ヶ月で元に戻ってしまうことが多いのが現実です。
近年では、「リペア」と呼ばれる技術も出てきました。
これは、劣化したハードコートを除去し、表面を専用の薬品で科学的に処理・再定着させる方法で、耐用年数はおおよそ2年程度。従来の研磨よりははるかに進歩しています。
しかし、ここで注目したいのがプロテクションフィルムの存在です。
紫外線の影響を直接防ぐことができるため、理論上の耐用年数が約7年と非常に長く、保護性能の高さが実証されつつあります。
コーティング剤の中にも「UVカット性能」をうたった製品はありますが、プロテクションフィルムの遮断性能とは次元が異なります。
(※誇大広告も少なくないため、気になる製品があれば「商品名+紫外線」でYouTubeなどで検証動画を調べてみるのが有効です。)
つまり、プロテクションフィルムを扱える技術を持つことは、単に技術の幅を広げるだけでなく、「車を長期的に守る」というコーティングの原点を、実現可能な形で追求していることの証でもあるのです。